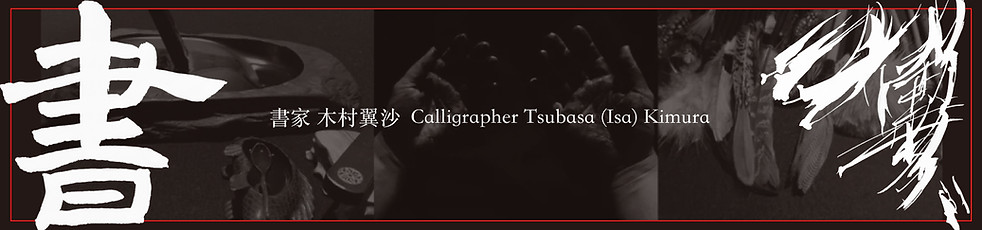【保存版】小筆の持つ位置で変わる文字の印象|軽やかさと力強さを使い分ける方法
- kimuratsubasa2
- 2025年10月1日
- 読了時間: 3分
更新日:1月3日
小筆は「どう持つか」だけでなく、「どこを持つか」によっても文字の印象が大きく変わります。同じ字を書いても、筆を上で持つのか、下で持つのかで線の軽やかさや安定感はまったく異なるのです。
本記事では、筆の持つ位置による線の違いを中心に、実用書に適した持ち方、そして和歌などに見られる昔の人の持ち方との違いまでを解説します。
👉 前回の記事(基礎編)では「鉛筆を応用した小筆の正しい持ち方」をご紹介しましたが、今回はその続編として、より応用的な「持ち位置の工夫」をテーマにしています。
筆を持つ位置で変わる線の印象
同じ文字を書いても、筆を持つ位置が変わると線の表情が変わります。
上方を持つ → 線が伸びやかで軽やか(リーチが長くなる=筆を大きく動かせる)
下方を持つ → 線が安定し力強い (リーチが短くなる=筆をコントロールしやすい)
たとえるなら、同じフォントでも「明朝体」と「ゴシック体」のように印象が異なるのです。日常での実用書はもちろん、作品制作でも「どんな線を出したいか」によって持ち位置を変えるのが効果的です。

実用書では「下方持ち」が基本
宛名書き、のし袋、賞状など、正確さ・読みやすさが求められる実用書では、筆をできるだけ下で持ち、安定させるのが最適です。
軸がぶれにくく、細かい線のコントロールがしやすい
起筆(書き始め)や止めが明確に出せる
「読みやすさ」を最優先にした線になる

基本の位置は「軸の真ん中より少し上」
一方で、筆の「標準的な持ち位置」は軸の真ん中よりやや上です。これは書の種類や作品の目的によって使い分けると良いです。実用書では下方持ちを優先すると良いでしょう。
昔の人の小筆の持ち方の一例

写真のような持ち方は、和歌を書く際に用いられた小筆の持ち方の一例と考えられます。筆を立てて支え、膝や片手で紙を押さえながら書くこの姿勢は、現代の私たちが日常で行う持ち方とは大きく異なります。
当時の人々は、生活の中で自然にこの体の使い方を身につけていたため、特別な技術ではなく日常的な動作として書けていたのでしょう。現代人が同じように再現するには、慣れない筋肉を使うため難しく感じることもあります。
👉 実用書においては「安定性重視の下方持ち」が適していますが、古典や和歌の学習では、このような昔の持ち方を知っておくことで、書の歴史や背景をより深く味わえるでしょう。
まとめ
筆の位置を変えるだけで、線の軽やかさ・力強さが変わる
実用書では「下方持ち」が安定性と読みやすさのために最適
基本位置は「軸の真ん中より少し上」だが、目的に応じて調整可能
和歌などでは、膝や片手で紙を支えて筆を立てる独特の持ち方があった