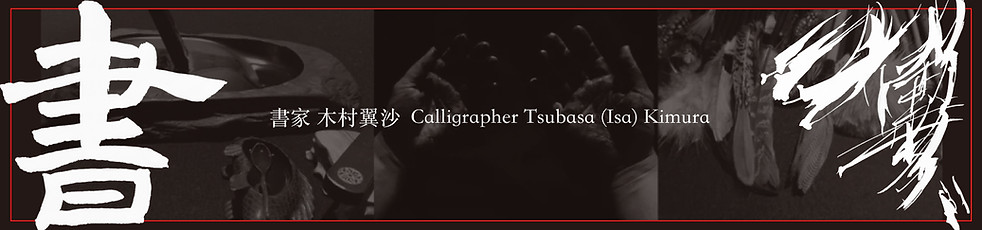【保存版】実用書における小筆の正しい持ち方|鉛筆から学ぶ基礎
- kimuratsubasa2
- 2025年9月30日
- 読了時間: 3分
更新日:1月3日
実用書と仮名では持ち方が違う
「小筆の持ち方」とひとことで言っても、実用書と仮名書道では目的が異なります。
実用書(宛名書き・賞状・のし袋など) → 文字を正確に、誰にでも読みやすく書くのが目的。筆は安定が第一。
仮名(和歌・短冊・料紙作品など) → 流れるような線やリズムを表現するのが目的。
👉 本記事では、実用書における小筆の正しい持ち方に特化して解説します。
小筆の持ち方はなぜ大切か?
小筆の持ち方は文字の美しさに直結します。誤った持ち方だと線が弱くなり、手や腕に余計な力が入り、書くのが苦痛になります。正しい持ち方を身につければ、楽に・安定して・美しい楷書を書くことができ、実用書全般がぐっと書きやすくなります。
実用書に適した小筆の正しい持ち方
1. お箸の持ち方をイメージ
正しいお箸の持ち方を思い出しましょう。上のお箸は人差し指と中指で軽く動かし、親指は添えるだけです。指の形、上のお箸はそのままで、下のお箸だけ抜いてみてください。(筆で実際に試した写真1・2をご覧ください)
2. 鉛筆の持ち方へ
そこから、筆の位置を調整します。筆部分が指に近づくように筆を上方に引っ張るイメージです。(写真3)この形のまま、筆の先が紙に触れる位置まで指を下げます。実は、これは鉛筆の正しい持ち方ともいえます。(鉛筆の場合は親指が人差し指と重ならないようにする)いずれも指先に余計な力を入れず自然に支えているのがポイントです。(写真4)
3. 小筆へ応用
この鉛筆の持ち方のままだと、筆が斜めに寝た形になりますが、そこから、筆を立てください。(写真5)これが実用書の筆の基本の持ち方です。





鉛筆持ちのままではダメな理由
鉛筆を持つ形のまま筆を使うと、筆先が寝てしまい、紙をなでるような弱い線しか出ません。筆を立てれば、円錐の頂点である筆先が紙に接し、しっかりとした「起筆」が生まれます。
実用書における起筆の基本角度は約45度。この角度が最も安定し、美しく、読みやすい線を生み出します。
力を抜いて疲れない持ち方を
実用書の小筆は、力を込めて支える必要はありません。お箸を持つときに「疲れた」と感じないように、筆も自然に支えるだけで十分です。大事なのは「力を入れること」ではなく「動きをコントロールすること」。無駄な力を抜くことで、長時間書いても疲れず、線も安定します。
実用書の小筆の持ち方・まとめ
小筆の持ち方は「鉛筆の正しい持ち方を起こす」のが基本
実用書では筆をしっかり立てることで、美しい楷書が書ける
起筆は45度が理想的な角度
余計な力は不要。自然に支えるだけで疲れない
実用書は「誰かに読んでもらうための文字」です。安定した小筆の持ち方を身につければ、宛名書きや賞状、のし袋など、あらゆる場面で自信を持って文字を書くことができます。ぜひ基本を押さえて、日常の実用書に役立ててください。
👉 次の記事では「持ち方を変えるとどうなる?(応用編)」として、線の変化や書きやすさの違いを詳しく解説します。