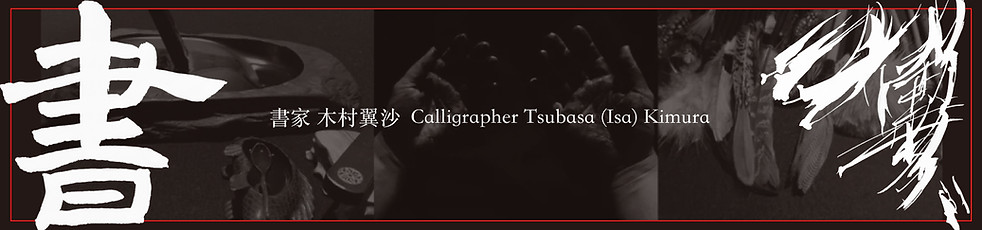
鳥筆100「風」
100本の筆、100の線、100の呼吸。
本作《鳥筆100「風」》は、100本の鳥筆を自ら制作し、それぞれの筆で「風」の文字を記した。2011年、大阪のTSUBASA KIMURA Museumで初展示され、のちの《鳥筆100》シリーズ全体へとつながる第一歩となった。
【会場写真】


《鳥筆100》「風」展示風景
鳥の羽でつくった筆による100点の作品を、壁一面に展示。種類も大きさも違う、それぞれの鳥筆の特徴を生かした「風」。
TSUBASA KIMURA Museum (大阪), 2011
【鳥筆とは?】
「鳥筆」とは、鳥の羽で作られた筆のこと。(通常の筆には、山羊や馬の毛などが使われる。)
書道における文房四宝の中でも、特殊筆の一種にあたる。「とりふで」という呼び名は、制作と使用を重ねるうちに、自然と定着していった。
鳥筆

通常筆

鳥筆の使い方

現在では特殊筆の一種とされているが、その歴史は非常に古く、今からおよそ1000年前、中国・宋代の書家、蘇軾(そしょく・1037–1101/蘇東坡)も、鳥の羽から作られた筆を使用していたことが知られている。中国には、羽の向きに沿って軸を回転させながら書く技法があり、これにより通常の筆に近い線質を得ることができる。しかしこの方法では、これらの筆特有の表現にはならず、どの作品に使われていたのかは、外見から判別できない。
日本の戦後前衛書において、「破線」の表現をめぐり、これらの特殊筆が使われていたとされる。鳥筆の可能性は、その「破線」の中に、これまでにない表現の気配を見出すことができるのかもしれない。
鳥筆の作り方



鳥筆は、鳥の羽から生まれる筆。まずは、さまざまな鳥の羽を手に入れるところからはじまる。それぞれの羽を丁寧に分け、筆に使える状態へと整えていく。羽の種類や向きによって使える部分が異なるため、気の遠くなるような作業になることもある。そして、筆職人の協力も得ながら、一本一本の長さと形を整え、筆として静かに組み上げていく。
なぜ「100」なのか。
一つの形にたどり着くには、少なくとも100の検証が必要になる。 《鳥筆100》は、その検証の記録であり、線の旅である。
その旅には、100本の筆が必要だった。 自らの手で筆を作り、その一本一本に問いを託して、線を刻んだ。
ここに、その軌跡がある。
100本の鳥筆コレクション(展示会場より)

【作品一覧】
└ No.1–20




















【作品一覧】
└ No.21–40




















【作品一覧】
└ No.41–60




















【作品一覧】
└ No.61–80




















【作品一覧】
└ No.81–100



















