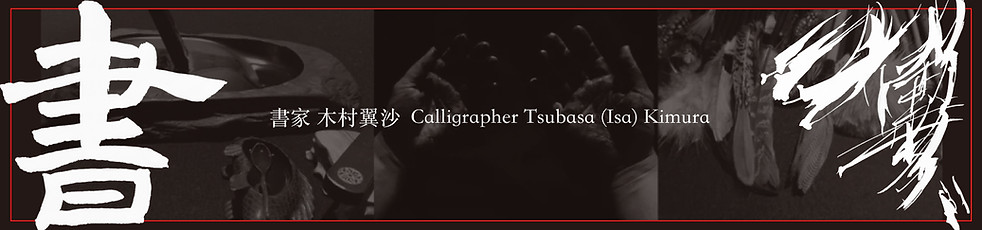
HOME > 書の世界 >Special Projects>素材探求作品
素材探求作品
素材が語る、書の声。
このページに収められた作品群は、書の表現を多様な素材に託した実験的な試みである。異なる素材�の特性を探ることで、書の線は新たな表情と可能性を獲得している。いずれの作品も小規模ながら、素材と書の関係を再考する重要な探求の一端を示している。
【10周年記念展・未来の間より】(2008年)
2008.11
「木村翼沙10周年記念書展」
会場:兵庫県立美術館(兵庫・日本)
ー活動10周年を記念した大規模個展において発表。
同一モチーフの素材展開
万年カレンダー表紙

「一二三四五、、、」
書:鳥筆
ステンレスカット

「一二三四五、、、(万年カレンダー表紙)」
A4サイズ、3mm厚
3D CAD/CAMアルミ削り出しペン

「九三十三十一(万年カレンダー表紙の最終行)」
刺繍

「一二三四五、、、(万年カレンダー表紙)」
A4サイズ
ひらがなの展開
ひらがなフォントマトリックス

いろは将棋

手作り将棋駒
漆
立体印刷

「彗星」
高さ 100 cm x 幅 50cm
パネル、立体特殊インク

「銀河」
高さ 100 cm x 幅 50cm
パネル、立体特殊インク
有田焼

�【手漉き和紙シリーズ】(2005年)
一枚ごとに異なる響きをもつ、和紙との対話。
全国各地の職人による手漉き和紙を用い、それぞれの紙に応じて墨と筆を選択し、作家独自の作風を施した作品。
2005
「手漉き和紙シリーズ」
会場:新風館3F トランスジャンル(京都・日本)
― 《Crowd》と同時企画として発表。
*作品寸法は本紙サイズです。
未完成の未の部分

高さ 44 cm × 幅 55 cm
額装
生漉奉書紙(越前和紙)/岩野市兵衛(人間国宝)、墨
ある個
水の水槽

高さ 38.4 cm × 幅 54.5 cm
額装
酒ラベル紙(因州和紙)/中原隆、墨

高さ 65 cm × 幅 25.4 cm
額装
美栖和紙(吉野和紙)/上窪正一、墨
宇宙の法則

都市の線

高さ 92.7 cm × 幅 63 cm
額装
雁皮紙(阿波和紙)、墨
高さ 137 cm × 幅 72 cm
額装
雲龍紙(因州和紙)/中原隆、墨
認知的不協和

高さ 143 cm × 幅 31.7 cm × 2
パネル
宇陀和紙(吉野和紙)/福西弘行、墨
無意識

高さ 97 cm × 幅 64 cm
パネル
よし紙(近江和紙)/成子哲郎、墨
機械仕掛け

高さ 97 cm × 幅 64 cm
パネル
自楮板干し(門出和紙)/小林康生、墨
自他の関わり

高さ 134.8 cm × 幅 42.2 cm
パネル
楮粗すじ紙(出雲民芸和紙)/安部信一郎、墨
【紙布+鳥筆】(2011年)
《鳥筆詩選》
ことばと空間のあいだに
紙布(しふ)��と呼ばれる、糸のように織られた特殊な和紙を用い、ミュージアムのモダンな建築空間に余白を生み、場と響き合うことを意識した作品群である。
題材は、古典詩歌や俳句、そして時代を越えて響く日本語のことば。その力を、鳥の羽根で作った筆により、現代に書として結晶させる。
【会場写真】


2011
「鳥筆詩選」
会場:TSUBASA KIMURA Museum (大阪・日本)
ー鳥筆による5点の大作。詩と書が空間で響き合う。
『平家物語』祇園精舎

120x240(cm)
祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。
松尾芭蕉の句

120x240(cm)
五月雨や集めてはやし最上川
閑さや岩にしみ入る蝉の声
秋深き隣は何をする人ぞ
面白し雪にやならん冬の雨
鴨長明『方丈記』

120x240(cm)
行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。玉しきの都の中にむねをならべいらかをあらそへる、たかきいやしき人のすまひは、代々を經て盡きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。或はこぞ破れ(やけイ)てことしは造り、あるは大家ほろびて小家となる。住む人もこれにおなじ。所もかはらず、人も多かれど、いにしへ見し人は、二三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。あしたに死し、ゆふべに生るゝならひ、たゞ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。又知らず、かりのやどり、誰が爲に心を惱まし、何によりてか目をよろこばしむる。そのあるじとすみかと、無常をあらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。或は露おちて花のこれり。
松尾芭蕉『奥の細道』
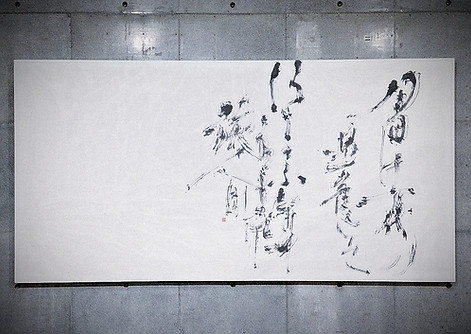
120x240(cm)
月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人なり
春夏秋冬(『枕草子』より)
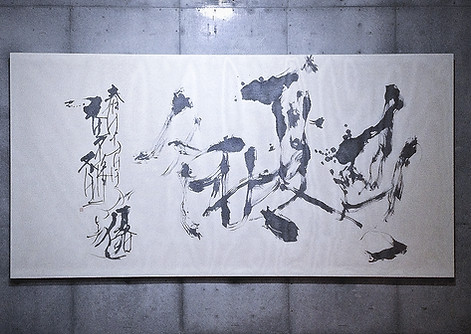
120x240(cm)
春はあけぼの 夏は夜 秋は夕暮れ 冬はつとめて