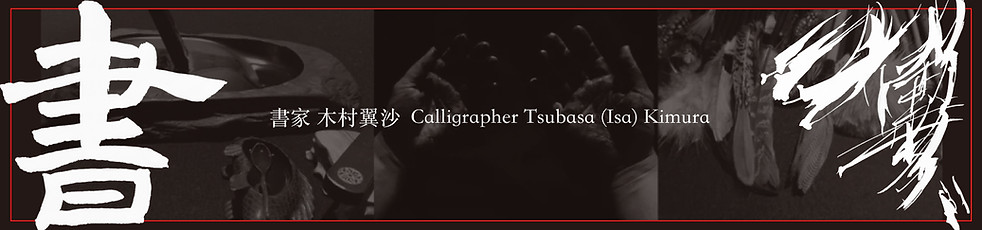「石鼓文」時代に翻弄された文字の話ー亡失と再発見の末に
- kimuratsubasa2
- 2023年5月23日
- 読了時間: 4分
漢字の歴史は、気が遠くなるほど長く、奥が深く、全くどうしてこんなに面白いのだろう、そう思うだけで、私の生きる糧になるほど、魅力的で楽しいものです。この人生に書道との出会いがあって良かった。この歴史を守り、育んできた国も素晴らしい。どうか、この国に一刻も早く平穏な日々が戻り、いつまでも、この素晴らしい文化が受け継がれていくようにと願っています。
漢字が辿ってきた道を見ていくと、たくさんの物語があります。激動の時代と共に消えていった文字、新たに生まれた文字…様々な要因があって、複雑に絡み合いながら、その都度完成しては、また進化を遂げ、至極合理的に、時代に適応していくのです。(時代に翻弄される、と言った方が良いかしら)
近年、毎日およそ8万人という桁外れの来場者が訪れる北京の故宮博物院に「石鼓館」と呼ばれる展示室があります。非常に貴重な文化財が展示されていますが、故宮博物院の他の華やかな建築や展示物に比べると、そこは、10個の黒い花崗岩の「石」が並んでいるだけであるから、地味であることは否めない。そして、この「石」の来歴を知らないと、何が何だか分からない渋い展示室と感じることでしょう。したがって、喧騒の中の故宮にあって、時が止まっているかのような静けさで、書道ファンにはたまらない贅沢空間となっています。

さて、この「石鼓館」に展示されている「石」について。これは、形が太鼓に似ているため「石鼓」と呼ばれ、そこに刻まれた文字を「石鼓文(せっこぶん)」と言います。中国最古の石刻文字資料であり、大きさは縦横約60㎝程度で、10個が一組となっています。その内容は、狩猟を描写した四言詩で、当時の王の暮らしがわかる文献資料の一つとしても重要です。製作年代については諸説ありますが、現在では、戦国時代(紀元前403〜221年)の秦で作られたと考えられています。つまり、秦の始皇帝が中国を統一し、文字を統一する以前の書体ということになります。

これまで、本連載中に「甲骨文字(亀の甲や牛の骨などに刻まれた文字=殷代)」・「金文(青銅器に鋳込まれた文字=殷・周代)」・「小篆(始皇帝が統一した文字=秦代)」を紹介してまいりましたが、今回の「石鼓文」は、「金文」と「小篆」の過渡期に用いられた文字で、両方の要素を兼ね備え、「小篆」に対して、「大篆」と呼ばれ、文字史に特異な位置を占めています。そして、実は、現代の「篆書」という書体は、これら全てを総称したものです。
「石鼓文」は、唐代(618〜907年)の初期に、現在の陝西省の陳倉で突如発見されました。その時から、破損が見られたそうですが、出土直後も雨ざらしの状態で、保存措置がとられるようになったのは、800年頃のことと言われています。その後も戦乱のたびに亡失と再発見を繰り返し、その間、破壊や磨滅により、はじめは700字以上あったはずの文字が、今では、半数以上も失われ、272文字だけが解読できるものとなりました。
石鼓文の災難として、最も有名なものは、1052年、行方不明になった一基が、上半分を切られ、中を削られてしまい、民家で石臼として使われていた状態で発見されたエピソードです。その際に、詩文の上半分も消失してしまいました。しかし、痛ましい姿になった石鼓は、残念ではありますが、石臼となり半分になった姿もまた、当時の状況を表す貴重な物語として語り継がれ、今ではそんな数々の困難にも打ち勝ち、残された存在そのものが誇らしく感じられるのです。

「石鼓文」は、数奇な運命を辿り、ようやく広大な故宮博物院の一室に落ち着きました。ガラスケースに整然と陳列された石鼓文は、他の石碑類と異なり、角がなく、丸みがあってふくよかで、石でありながらどこか温かく愛嬌があり、大陸中を転がり続け、ようやく安息の地を得たるような、穏やかな佇まい。私は思わず「みんな、よくここまで踏ん張ってきたね」なんて、労いたくなるほど感慨深く、石鼓たちも「もう、離れ離れになるのはごめんだから」なんて、言っているようで、二千数百年も前の景色や、古代の人の思いを、今に生
きる私たちに、静かに、優しく、伝えているようなのです。
(本稿は奈良新聞連載エッセイ「暮らしの中の書」2020年2月13日掲載分)