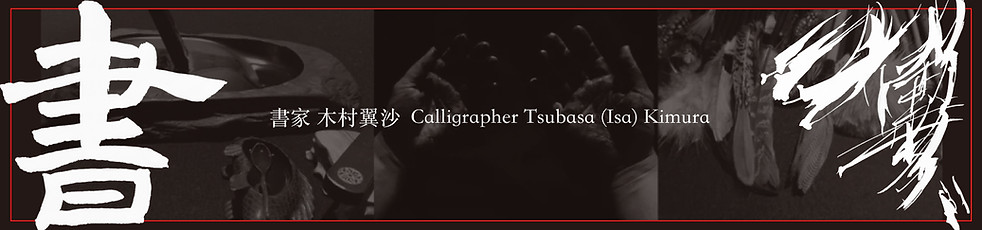「竹簡・木簡」の話ー区別難しい2種の素材。書写材料の伝来を物語る。
- kimuratsubasa2
- 2023年5月25日
- 読了時間: 4分
これまで、古代中国における、文字を表すための書写材料として、様々な素材をご紹介してきましたが、今回は、竹や木を細長く短冊状に削った札、「竹簡・木簡」について書きたいと思います。現代の私たちが文字を書くために、当たり前に使っている紙は、現在知られている最古の漢字が完成してから、およそ2000年、亀の甲羅や動物の骨、石や青銅、絹、竹や木など、環境や時代に応じて、様々な素材を経て、ようやく辿り着いたものです。それらの中で、紙が発明され、普及する以前、最もよく利用された素材は、実は、「竹簡・木簡」でした。
正式には、竹で出来たものを「竹簡」、木で出来たものを「木牘(もくとく)」といい、両者を合わせて「簡牘(かんとく)」と言います。日本では、「竹簡・木簡」の呼び方が一般的です。「竹簡・木簡」の起源については、明確には分かりませんが、現在、発掘され、知られているものは、戦国時代(前4世紀)から晋代(後4世紀)内のおよそ6-700年間で、その中でも、漢代(前2世紀−後2世紀)のものが圧倒的に多く、漢代を代表する書写材料と思われることがあります。
しかし、実際は、甲骨文字や金文にも「竹簡・木簡」と関わる文字があり、おそらく殷代(前17世紀−前11世紀)には既に普及していたと考えられます。これらは地中で腐りやすく、保存が難しいため、残りませんでした。今日見られる「竹簡・木簡」は、極度の乾燥地帯や、保存のための処理が施されるなど、一定の条件のもとに残された大変貴重なものです。

中国湖南省の長沙に、国内初の「簡牘」博物館があります。そこには、主に、長沙市で発掘された貴重な「竹簡・木簡」が展示されています。そこを訪れ、「竹簡・木簡」を見ていた時、不思議だな、と思ったことがあります。それは、展示されている、いわゆる細長の縦に通る繊維や木目の片を「竹簡」とも「木簡」とも見分けられないことです。キャプションを見て、ようやく分かるのですが、書かれていない場合、全く区別が出来ません。保存のために、ケースに入れられ(保存液に浸されているものもある)、ガラス越しに直接見られないことが理由の一つかも分かりません。それにしたって、分かりません。

さて、「竹簡・木簡」の形状は、いずれも非常に細長く、一行程度しか文字を書くことができません。この独特の形は、竹の元の姿を想像すると納得できます。つまり、長さは、節から節まで、幅は、節を取った筒状から文字が書ける平面のサイズ、とイメージ出来ます。しかし、木であれば、その形に制約される必要がないと思いませんか?
最初から板のようにして、大きな面にすれば、もっとたくさん何行も書けたはずです。つまり、書写材料としては、先に竹が使われ、木簡は、竹簡の代用品として使われたのではないか、と考えられるのです。ちなみに、中国の一般的な「竹簡・木簡」のサイズは、用途によって多少異なりますが、長さ約23cm・幅約1cm・厚さ2-3mmです。(実際に発見された「木簡」は、幅広のものも多く、様々な形があります。)
ところで、中国において、木簡は、主に竹が成育しにくい乾燥地帯から発見され、竹簡は、主に竹の成育に適した、気候が湿潤な内陸部から発見されています。つまり、環境によって、入手しやすい材料に文字が書かれた、ということも想像されます。ちなみに、日本でもたくさんの「木簡」が発掘されています。しかし、竹の成育に適した環境にも関わらず、「竹簡」は見られないそうです。
皆さま、ご存知でしたか?(恥ずかしながら、私は知りませんでした。見た目の区別も出来ず、そのまま「竹簡・木簡」と一括りにしていました。)これは、中国から日本へ文字が伝来した時期(4-5世紀頃)に関係しているそうです。
日本に文字が伝わった時期には、中国では、既に紙が使われていましたが、まだまだ貴重な紙で、書写材料として「竹簡・木簡」も併用されていました。サイズも用途も便利な「木簡」が、「竹簡」の後から作られたのであれば、「竹簡」はもう使われず、日本には伝わらなかったのかも分かりません。しかし、日本に「竹簡」という言葉が残っているのだから、実際は「竹簡」も伝わっていたけれど、朽ちやすいため地中に埋もれてしまって発見されないだけかも分かりません。
それとも、当時の人たちも、私と同じように、区別がつかずに、「木簡」を指して、「竹簡」と呼んでしまったのかしら、なんて、勝手に想像して愉快な気分、なんて、古代の人には不愉快かしら。いえいえ、過去から現代と思いを巡らせ楽しむことが出来るのは、歴史が遮断されることなく、現代に続いている繁栄の証ですから、この先も絶えることなく、未来の人が歴史を楽しむことができますように。
(本稿は奈良新聞連載エッセイ「暮らしの中の書」2020年4月9日掲載分)